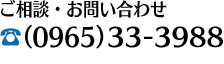Q&A
Q&A
登記手続きに関するよくあるご質問をご紹介します。
- Q1 不動産を相続しました。どういった手続きが必要ですか?
- A1 登記簿(登記情報)に登録されている所有者の名義を、相続人に変更する相続登記手続きが必要になります。しないといけないという義務ではありませんが、その権利及び責任を確定しておかないと、将来、相続人の子供、孫の代でトラブルの種になるので早めの手続きをお勧めします。
- Q2 不動産の権利書を失くしました。再発行はできますか?
- A2 昔は不動産登記(権利)済証という書面がありましたが、オンライン化によって、現在は登記識別情報通知書というパスワードが発行されるようになりました。どちらも再発行は出来ませんので、大切に保管をお願いいたします。
- Q3 相続人の中に行方不明者がいますが、相続登記はできますか?
- A3 他の共同相続人から法定相続分の単独申請は可能です。ただし、行方不明者との共有になるので、トラブルの先延ばしにしかなりません。相続発生前であれば遺言書を遺すことによって回避できますので、遺言書の作成をお勧めします。
- Q4 抵当権とは?また、抵当権の抹消とは何ですか?
- A4 住宅ローンの支払いが出来なくなった際に、担保として設定された土地、建物から優先弁済を受ける権利を抵当権と言います。借入の際に、設定の手続きは司法書士が行いますが、完済した際の抵当権の抹消は自動的には行われません。不動産を売却する場合、抵当権などがついていない状態で売ることが一般的ですので、完済されたときは抵当権の抹消手続き同時に行うことをお勧めします。
- Q5 親が認知症になりました。不動産の売却はできますか?
- A5 介護施設の費用にあてるためご自宅を売却されるニーズは高まっています。しかしながら、売主本人が認知症などで判断能力が低下した場合、売買契約及び登記手続きを行うことはできません。認知症になった後では、成年後見制度を利用するしかありません。認知症になる前であれば、生前贈与、家族信託といった対策も可能ですので、事前の備えをお勧めします。
- Q6 根抵当権の設定者が行方不明です。どうすればよいですか?
- A6 元本確定期日が定められていない場合、根抵当権者は、不動産の所有者に元本確定の請求をすることができます。請求の相手が行方不明で請求ができないときは、公示という方法で元本確定の手続きを行うことができます。
- Q7 農地をあげるときの許可とは何ですか?
- A7 農地を農地以外の目的で利用する。または、農地を相続以外の方法で譲渡しようとする場合、原則として、農業委員会の許可を必要とします。家を建てる。農地を売る。という行為は簡単にはできませんのでご注意ください。
- Q8 過料の通知がきました。過料とは何ですか?
- A8 会社設立後、会社の名前、所在、役員などの登記されている事項に変更が生じた場合、原則として2週間以内に、変更の手続きを行う必要があります。登記手続きを怠ると、過料という行政罰が科され、お金を支払わなければなりません。通知は会社代表者の個人宛に届きますので、経営者の方は、変更手続きを怠らないようにご注意ください。
その他、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。